favorites of q3e8mk![]()
![]()
今、洪水のタイの人口は6544万人 |
返信 |
データ | |
男女比は男性49・1%、女性50・9%で、女性が約120万人多い。
外国人は約330万人。 人口の45・7%は市街地に居住。
全体に占める各地域の人口の割合は東北部28・7%、中部27・7%、北部17・5%、南部13・5%、バンコク12・6%。
-ちなみにー
東南アジア諸国連合(ASEAN)
・ インドネシア 2億3800万人
・ フィリピン 9400万人
・ ベトナム 8600万人
・ タイ 6544万人
合計、4億8344万人
アメリカの人口は、3億875万人。 ASEANは、アメリカより約1億人多い。

村田製作所社長インタビュー |
返信 |
ニュース | |
村田製作所の村田恒夫社長は、読売新聞のインタビューで最先端以外の製品について海外生産に主軸を移す方針を示した。主なやり取りは次の通り。
--海外で生産拠点拡充を積極的に進めているが。
「海外メーカーの追い上げが激しい。最先端以外は(海外生産して)同じ土俵で戦わないと難しい」
--国内の生産拠点はどうなるのか。
「製品が陳腐化すると値崩れし、顧客にとっても魅力はない。新製品をだしていく必要があり、これは日本で作っていく」
--スマートフォン向けの電子部品が好調だ。
「スマートフォンだけでなく、家庭で使用する電力を制御するシステムの無線化も進む。通信機器関連はまだまだ拡大する」
--フィンランドのVTI社買収の狙いは。
「新たなセンサー技術を取り込み、機能を上乗せしていく "にじみ出し" で事業領域を広げたい」
デバイス技術と据え置き型リチウムイオン二次電池との関係は?
"使用する電力を制御するシステムの無線化も進む" このあたり。 デバイス技術と電池を合わせれば電池に付加価値がつく。(デバイスによって使い勝手や使い方のアイデアという付加価値をつける)
ここが知恵のしぼりどころ and 日本の個性の出しどころ。
‘NEC、マンガン系リチウムイオン二次電池の寿命を2倍以上にする技術を開 発’ |
返信 |
ニュース | |
>> NECはこの技術を活用した容量3.7Ahの電池を試作し、一般的な家庭のエネルギー消費のパターンで寿命予測を実施した。その結果、充電できる容量が初期の70%に下がる年数が、従来の約5年から約13年に伸び、50%までだと約15年から約33年になり、2倍以上、長寿命化することに成功した。耐久性の評価実験でも、2万3500サイクルの充放電でも初期容量の83%を維持することを実証した。
電池の基盤技術は、NEDOが低コスト、長寿命、安全性を追求した蓄電機器と蓄電システムの開発促進による再生可能エネルギーの利用拡大を目的に、 2011年7月に始めたプロジェクト「安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発」に利用する予定になっている。NECは今後、今回開発した技術をエネルギー密度の高い電池に適用するための研究を進める。
<<
かなりいいところまできた。 あともう少し。
2011年10月22日 オリオン座流星群が極大 |
返信 |
そういや ピューーと夜空を横切っていたよ
エージェントとコンシェルジュ |
返信 |
雑感 | |
・ エージェント → は代理人。 サッカーにおける代理人(選手エージェント)。
・ コンシェルジュ → はお世話役。
エージェントは、こちら側から向こう側に送り込まれる人。
コンシェルジュは、こちら側についてるときもあるし、向こう側についているときもある。 たとえば 腰の低い幹事さんと宴会場の世話人。 2人が緊密に情報を共有してイベントを進行させるなら2人ともコンシェルジュ。
エージェントは、主人の意図に沿い 自分で策を練って相手に条件を突きつける。(最適な交渉術で)(能動的)
コンシェルジュは、こうゆう別なやり方もありますよ、とプランBをアドバイスしてくれたり、選択しないといけない場面でヒントを示してくれたりする。(サポート、ガイダンス、アドバイス)
エージェントとコンシェルジュは、これからのIT分野で重要な概念になる(のではないか)。
反格差デモ 中国は.. |
返信 |
ニュース | |
>> 反格差社会デモの世界一斉行動日とされた15日、北京市中心部の繁華街では警察当局が警備を強化し、通行人らの警戒に当たった。中国でも格差拡大が深刻な社会問題になっており、一部海外メディアによると、北京、上海、江蘇省南京などでデモの呼び掛けがあったが、デモ発生は伝えられていない。
国営通信新華社などの中国メディアは米ニューヨークでのデモを報じているが、当局は中国国内に波及するのを警戒し、インターネット上では一部で「デモ」や「抗議」などの単語が検索できなくなっている。(共同) <<
---
徹底的な封じ込め。 デモはもうムリ。
‘富士通研、音声だけで情報収集できるモバイル端末向け技術開発’ |
返信 |
雑感 | |
>> 富士通研究所(川崎市中原区、富田達夫社長、044・754・2613)は13日、画面を見ずに音声だけで情報を取得できるスマートフォン(多機能携帯電話)などのモバイル端末向け音声技術を開発したと発表した。スマートフォンに向かって質問すると情報を自動的に探して答えてくれる。運転中や作業中などに情報収集できるツールになる。2012年度中の実用化を目指す。
例えば、スマートフォンが音声合成で読み上げた最新のニュース報道に対し、関連する単語を発すると、さらに詳細な情報を即座に引き出して読み上げてくれる。運転中のほか、博物館や展示会など詳しい解説が求められる音声ガイダンスサービスにも使える。
時事用語はインターネット上から「表記」と「かな」のパターンを自動で抽出し、単語辞書に順次、登録する仕組み。ユーザーが発した言葉に同音異義語があっても正しく理解し、読み間違いや誤認識は少ないという。 <<
---
おー、このニュースはタイムリー。(昨日 音声認識コンシェルジュ型UI のことをあれこれ書いた)
日本もちゃんと開発しているんだなー。 これをロボット研究で培われたAIと結びつけ、クラウドのフロントエンドにするんだ。
要素技術はちゃんとあるのに それらを結集させ統合する応用力に乏しいのが今の日本の現状。 技術が会社や大学にばらばらに存在していて結びつかない。 産学連携のプロジェクトチームを起せよ...
‘次期iPhoneは5ではなく…’ |
返信 |
雑感 | |
>> それでは、iPhoneはこのまま進化(evolve)はすれど革命(revolve)しないのだろうか?
するとしたら、プロトタイプはこれではないのか。そう。6代目iPod Nano。
iPhoneがiPodから生じたように、「次のiPhone」はiPhone nano、もしくはiWatchとして登場するのではなかろうか。 <<
ガジェットが大きかろうが小さかろうが音声は変わらない。 音声認識コンシェルジュ型UI(人工知能応答型UI) とクラウドの連携を完成させておけば 応答の結果表示はガジェットごとにいくらでも変えられる。
今 appleはapple流のやり方で音声UIを完成させ、一番乗りしようとしている。
クラウド |
返信 |
雑感 | |
クラウドというのは計算リソース(ストレージじゃなくcpu) が必要に応じてスケールするということなはず。
以前、池田氏は電子書籍(閲覧onlyの) をクラウドに置いてます、と言っていたけど それはストレージでしょ、と。
"自動で同期する" という表現があることでファイルの置き場所みたいなものというイメージが刷り込まれているような。(それはバックアップストレージ) ウェブ上のiCloud の解説を読んでいてそう思った。
iOSとOSX の垣根を越えて使えるにデータに変換する、というところで計算リソースを使っているからクラウド、ということなのか。 あるいは、クラウド型システムをまずはストレージとして使っていく、ということなのか。 (たぶん後者)
あのsiri (人工知能型応答システム) なんかはクラウドだろう。
UI に関しては、指でアイコンをたどるやり方と、音声で対話的にアプリを使うやり方 の2系統ということなのだろう。
UI を人工知能型応答システムにして向こうにクラウドを置けば フォルダの概念やアプリがどこにあるかなんて考えなくていい。 アイコンを1回2回 指で触って そのあと音声で対話的にファイルを呼び出しアプリを動かす というようなUI。 たぶん そんな方向に進む。
クラウドと人工知能型応答、この組み合わせのアイデアがappleの方向性なのかも。(言い方を変えれば、appleはクラウドをより感覚的に使うには人工知能型UI が必要になると気づいた、となるか。 それは確かにappleらしい。)
---
● ‘世界初の「考えるロボット」、東京工大研究所が開発’ - 
>> 長谷川氏の「自己増殖型ニューラルネットワーク(Self-Organizing Incremental Neural Network、SOINN)」は、既存の知識を参考にして、課題を解決するための方法を推測するアルゴリズムだ。SOINNは環境を分析して必要なデータを集め、与えられた情報を理路整然とした指示にまとめあげる。
仮に、SOINN搭載ロボットに「水をくれ」と言ったとしよう。研究所で行われた実演では、ロボットはその課題を、「コップを持つ」「ボトルを持つ」「ボトルから水をそそぐ」「コップを置く」といった既知のスキルに順序立てる。つまり、水を提供する特別なプログラムがなくても、課題達成のための行動の順番を自分で考えることができるのだ。
また、能力を上回る課題に直面したときには、助けを求め、そこで得られた情報を将来に生かすために蓄積する。さらに、モノの外見や単語の意味がわからないときには、インターネットを使って自力で検索をする。
将来的には、紅茶を入れることになった日本のロボットが、英国のロボットに入れ方を聞く、ということもできるようになるはず、と長谷川氏は語った。 <<
● ‘世界初! 構成を動的に変更可能なニューラルネットを用いたヒューマノイドロボットの動作学習に成功’ - 
日本もロボット研究の方面で人口知能の研究は進んでいる。 進んではいるけど、これをスマホ&クラウドに応用しようとはしていない。 appleは今それをやっている。(ちょい妄想入り)
---
メールを送るのにメニュー階層をたどって入力画面を出すんじゃなく、"「メール送りたい」" で入力画面が出て、"「誰々に送信」" であて先が指定され送信される。
視覚と指はメニュー型UIで、音声はコンシェルジュ型UI、なのかも。(合わせ技もある)
ステイハングリー ステイフーリッシュ |
返信 |
雑感 | |
秋が来ると自然にそうなる。
考えてみれば、ステイハングリー ステイフーリッシュ な状態ていようと努力すること自体がおかしい。
そこに努力があってはいけない。 努力はその状態の次にすること。
10月10日なんて秋のど真ん中。 それゆえ分岐点。 腹がへってしょうがない、をいい方にもっていこう。
ステイハングリー ステイフーリッシュ なんて難しいことじゃない。
難しいのは、ステイ勃起2時間 だろう。
ステイモヤモヤ ステイボッキ こそ原動力だ。
調べてもわからなかった |
返信 |
日記 | |
Chromeの拡張機能ページで,拡張機能によっては「ファイルのURLへのアクセスを許可する」ってのが「シークレットモードでの実行を許可する」の隣に表示されるわけだけど,「ファイルのURLへのアクセスを許可する」ってのがどういうことなのかわからないから,許可した方がいいのかしない方がいいのか判断できないんだよね。
「ファイルのURLへのアクセスを許可する」ってのはどういうことで,許可することのメリット/デメリットは何なの?
in stead of ~ の覚え方 |
返信 |
英語 | |
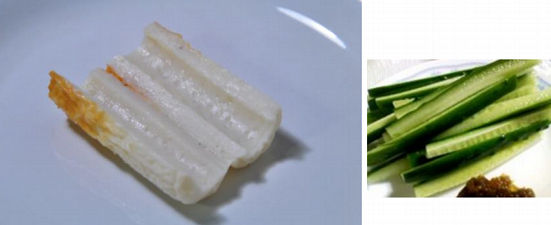
インスティ で切って
スティ は スティック → きゅりりスティック → きゅうりスティックは棒 → 棒は穴を求める →
棒と穴を連想 → であるなら きゅうりスティックは 置き換えられる → きゅうりの代わりに
ということで、"~の代わりに"
中スティック と覚えておく。
例文 :
100 Books You Should Read Instead of Going to Business School.
ディスプレイ3D なのか 3DCG なのか まぎらわしい |
返信 |
Disp3D、 3DCG、 と表記してほしいな。
リチウムイオン電池 |
返信 |
ニュース | |
● ‘GSユアサなど3社、電気自動車用電池7割増産 ’ -  (日経)
(日経)
受注先 :
三菱自動車
仏プジョーシトロエングループ(PSA)
カナダの自動車部品大手マグナ・インターナショナル
● ‘エリーパワー、大型リチウムイオン電池生産能力6倍に ’ -  (日経)
(日経)
>> 大和ハウス工業などが出資する蓄電池製造ベンチャーのエリーパワー(東京・品川)は2012年春にも川崎市で新工場を稼働させ、大型リチウムイオン電池の生産能力を今の6倍に引き上げる。従来の公共施設・事務所用に加え、住宅など家庭用にも本格参入する。総投資額は150億円。東日本大震災後に電力不足への懸念が全国的に高まるなか、自然エネルギーなどをためる蓄電システムの引き合いが増えていることに対応する。 <<
----
徐々にエンジンがかかってきた。
何年も前からアナリスト達は、2012年に蓄電池産業がブレイクすると予測していた。
2011年後半、それがきっちり現実化してきた。 さて、来年 そしてそこからの10年どうなるか。
気がつけばエネルギーのあり方を変えてしまっているかもしれない。
